詩を編む(1)
永瀬清子の詩を中心に書き残したものを紹介してゆきます。
時間の味方

あの人は才能もあり 美しくもあるのに、時間に負けている。
それは今持っているものの利をたのみすぎ、自分と人に尽くさないから
時間は意味なく過ぎ彼女を助けないのだ。
本当は太陽が稲を実らすくらい、時間は我々を照射しているので、
私たちは今すぐのプラスを考えないでも、
おもむろの成熟があり、それが「時間の味方」と云えるのにーーーー。
彼女は自分で打算しすぎ、彼女の方からは待たないのだ。
正宗白鳥先生の偏屈
岡山市 後楽園内にある「鶴鳴館」
長島からのかえりのバスで橋本富三郎氏が 十月二十七日の正宗白鳥氏と光田園長の文化勲章の祝賀会に、あなたが正宗さんへの祝辞をのべる事を承知していられるんでしょ?とたずねられた。
私は「いいえ」と答えると、そんな筈はない。もう御願い状が行っている筈だがと首をかしげられた。「然しそれは準備会できまった事だからまちがいはない。是非一つ詩をかいて来てよんで下さい。」と云われる。「私 白鳥氏の祝辞なんてとても書けません。私より大学で文学やってる先生が沢山あるでしょう」「じゃあ誰があるか云って下さい。」とまじめな顔。「だって私 お名前知らないですもの。」「ね、誰だって判りません。ぜひ貴女やって下さい。」「もっとも白鳥氏がロマンチックな方でしたらね。」押し問答しているうちに事務所へバスがついた。短い停車時間に橋本氏は新聞社へ電話をかけてやはり私が祝辞をのべる事になっているのをたしかめられた。白鳥氏は県で祝賀会を開くからと云っても仲々おみこしをあげて岡山へ来て下さらないので、夏頃からみんな関係当局の人々がてこずっていると云う事をかねてからきいていた。そんなのに私が詩をかいたり、祝辞をのべたりするのはヒジ鉄を食っているのにラヴレターをかくようであまりいい役廻りとは云えない。然し翌日又山陽社会事業団から電話で頼んで来たりして、白鳥氏ほど気の強くない私は とうとう押しつけられてしまった。
でもそれからの一週間は雨で麦まきがおくれたので、二十七日の朝は早く起きて撒き終わり、きちきちの時間にやっと汽車にとびのって公園の鶴鳴館へいそいだ。行ってみると まんまくを張りめぐらせてありとても物々しい。私はうまく感想がのべられるかと心配になったが、でもほかに云いようがなく自然な事をのべさえすればと自分で自分を落ちつけた。控室には誰もまだ見えてなかった。光田氏の祝辞をのべる光明園長がみえ、橋本さんがみえ、シトロハイムのような谷口山陽新聞社長が見え、女傑の山陽女学校長 上代女史もみえた。光田園長は井上さんに手を曳かれて来られた。正宗得三郎氏が肩からバッグをかけて来られ、白鳥氏代理の正宗敦夫氏はモンペ姿地下足袋で来られた。白鳥氏に贈る瀬戸内海の絵をかかれた中山巍画伯も来られた。すべて風雪を経、年輪をもった人々の中で 私はひとり場ちがいに思われる。ベルが鳴りみんな会場へ立たれ、私は事務長の井上さんを手つだって光田氏に勲章をかけてさしあげた。
会場は随分の人でぎっしりであった。谷口社長の挨拶にはじまり、知事の祝辞の代読、その他お歴々の型通りの祝辞があった。林岡山大学長と光明園長の光田氏をたたえる言葉があった。林学長が明治四十年頃、光田氏の講義をきいた時、患者の頭蓋骨の標本をもって来られ、講義の途中「ここからこんな風にはげます」と云いながら、ひょいとその標本をかぶって見せられたのに驚いたとおっしゃった。いよいよ私の番になった。
「私に祝詩をと云われましたが、私にはとても白鳥氏の詩はかけません。しかし三つの意味で
私はここへまいりました。一つには白鳥氏がこの祝賀会に出席されない正直な頑固さを尊敬するため、二つには然しその事を こうして大勢のお集まりの中には理解できないで、不服に思ったり割切れぬ気持ちを抱いていらっしゃる方も少なからずおありと思いますので、文学にたずさわって居ります私には いささかその気持が判るように思えます所から当たらずと云えども遠からずと云う そのわけを考えてみたいと思うため、今一つには その頑固な白鳥氏への御返礼を一本まいらせたいためで御座います。」とやりはじめた。一杯になっている人々は型通りの挨拶とはちがうなと、みんな にこにこ笑っているので私も話しやすくなりはじめた。
「第一については何より私自身でよく反省し、あやかりたいので別にここでは申し上げません。
第二については まず何より白鳥先生は文化勲章をおもらいの事を大して名誉とも嬉しいとも思っていられないと云うことが最大の理由であると思います」ここで人々はざわめきおやおやと云った感じ。
「なぜならば政府と云うものは決して白鳥氏の文学を理解し、それで勲章を呉れたのではないと云う事を白鳥氏は知っていらっしゃるからで御座います。たとえば戦争中「細雪」を書いてはならぬと禁止した政府は、舞台が変わればたちまち谷崎潤一郎氏でなくてはならぬと勲章をさずけて居ります。
それは世間の盲千人の総音頭が政府であって、本当にその価値を理解しているのではないためと思います。だから又舞台が一廻りすれば、何時白鳥氏にも書いてはならぬと禁止がくるかも知れません。
そうした政府に賞をもらっていい気になる事は白鳥氏として出来ないとお考えなのだと存じます。
又次には こうした大掛かりな祝賀会が大抵空虚な虚礼であって、自分に大して関心をもっていない人々が面子の立てあいで催し、自分が知りもしない人にぺこぺこ頭を下げ通しにせねばならぬと云う事を知っていらっしゃるからで御座います。こう云いますと文学者とはなんと傲慢なものだろうと皆様はお考えでしょうが、それはそうとばかりも云えないので御座います。又一方次の理由で考えますと白鳥氏は自分が今まで郷土のためと思って小説を書いた事は一度もない。それは国家のため政府のために書いたのでないと同じに、郷土のために何をもつくした事がない。ただあるがままに作品を書いたので、今更郷土の人々が誇りだと云ってお祝いするとしても、どうしても のこのこ出かけて行って花輪をもらうのが気はずかしいと、こう思われるのも文学者の正直な心であり又美しい はにかみの心であります。それをお察ししなければならないと思います。
けれども私はそれだからと云って ここにこうしてお祝いの会を県民こぞって挙行すると云うことは、又ことにこうして沢山の方々の熱心なご参加を拝見しては、決して無駄なこと、いらぬお世話だったと思っているのではありません。私は白鳥さんが たとえどう思っていらしても私たちが誠意をもってお祝いする事を心からほほえましいこと、又嬉しいことに思っている者で御座います。ですからここに あめのうずめの命そっくりの顔をして出て来て、そうか そんなに面白い会だったのなら僕(わし)も行ってみればよかったと思わせたいためのおしゃべりをしている次第で御座います。
そして白鳥氏がいろいろの意味から出て来れなかった事も、白鳥氏としては無理からぬお気持ちではありますが、県民の心として考えればやっぱり彼は頑固おやじにちがいありません。そこで出て来られぬ返礼に私は何か一本まいらせたいと思うのでありますが、丁度私の友だちの岩田潔と云う俳人が正宗白鳥と題しましてこんな面白い事を云って居りますので、それをお粗末ながら進呈して今日出て来ぬ面当てに いたしたいので御座います。それは正宗白鳥はやっぱり立派な芸術家でありまして、いつも冷静な心で世に中を批判して居ります。いつも現実をみつめて人間性をむしろ冷たい位にみつめて居られます。そうした芸術境を岩田さんは曰く、白鳥の芸術こそ「胃散をのんでいる厭世主義者」だと云うのであります。つまり本当の厭世主義者なら さっさと世の中をおさらばしたらいいでしょうに、白鳥氏はいかにも厭世主義のようなことを口にしながら、自分の健康だけは大事にして、充分保養していると云う皮肉な観察なのであります。もし今日の御欠席をどうしても気にくわぬと思う御方は私のこの御返礼の言葉で腹の虫をおさえていただきたいので御座います。」
思いがけぬ大変な喝采の中を私は引さがった。とにかく儀礼的に固くなりがちの今日の会を大いにほぐらかしただけはよかったらしい。私は丁度原稿のいそぐのがあったので、すぐに控室へ行って一人で書いていると やがて井上さんが入って来られて「今の敦夫先生の御挨拶をおききなさいましたか。」と云われた。「いいえ。」と答えると、「白鳥氏の心持ちは彼女のおっしゃる通りだと太鼓判を押されましたのです。」と笑いながらおっしゃった。出来上がった原稿を託す人を探していると上代校長が、「あなたよく云ってくれましたね。」と肩に手を置いておっしゃった。それからお歴々の人々についてすぐ傍の浩養軒で御食事をよばれたが、まるで私が花形のように一躍人気者になった感じだった。そして今日の会をあなたが活かして下すったと橋本さんもよろこばれた。私は、この間の長島で、話し方の手ほどきを貴方にしていただいたのですと答えた。
翌日ローカルで私の話の録音放送があり又次の日にはAKの方から再び放送された。私はただ自分では全く思った通りのことをいったのにすぎなかったが、口の重い私の話がそれほど歓迎をうけたことははじめてだったから、随分驚きもし、やや得意にもなったが、それからしばらくして西大寺にいる義弟の保太さんに行き逢うと、「この間 村長に駅で会ったら、白鳥会の割当は村の方でまかなうからよろしいですよといってくれたのはいいが、僕が会はどうでしたとたずねた所『それがね、いやはや とんだ事でしたよ、何とかいうへんな女が出てきてね、はじめから終わりまで白鳥先生の事を糞味噌にやっつけたんでさあ』といってましたよ。僕はそれが僕の姉さんだとはいえないから笑っていましたけどね。」といった。私はあれほど条理正しく話したのにそんな風に どうしてとられたのかさっぱり見当がつかなかったが、なるほど世間というものは広大であって、私が考えているよりはるかに考えも言葉も通じない人類も沢山あるし、決していい気になるべきではないという事を改めて得心がいったのであった。
橋本さんが首を傾けられた依頼の手紙は 会のあと二三日すぎて家から十キロも離れた潟瀬村宛の上にエブが沢山ついて回送されて来た。
金糸のぬいとり ー後楽園の あてつまんさく
註 あてつまんさく-----吉野善介先生により岡山県阿哲郡(現新見市)で
発見され この名がある。
やっとよみがえった春の光が
しずかに この園に満ちそめると
金のぬいとりを先ず刺すのは
あてつまんさくの花の細糸
下枝に あゆみ寄る旅の娘らは その横顔に
季節はずかしく まだ来ぬ時への望みをたたえ
その胸のあたりに金色の針が
縫っているよ 誰かのイニシャルを
しなやかにのびた その瑞枝を
すかし彫の扇のようにひろげ
人もまだ少い春寒の芝生に
ひとところ光線をたばねて
ちろちろ小さく燃えているよ
かわいらしい金のたいまつが
深尾さんの一周忌
深尾須磨子さんの一周忌の法事に、私は明石のお寺にいった。
港野喜代子さんもそこで落ち合った。
一緒に本堂の一隅に座ってから、私は彼女に「どれだけ包んで来た?」とたずねた。
それは彼女の包んだ香料と、私の香料とにあまり差があってはバランスが悪いと
人並みに思ったからであった。
彼女はすぐ「私はこれ。」と云って膝の前の小さいビニールの植木鉢を指した。
見るとその小さい鉢には紫の菫の花が植えられて居り、いつか崖の上の彼女の庭一めんに
咲いていたその種類にちがいなかった。
「それに私は弔詩も書いて来たよってに」と彼女はつづけて云う。
なるほど。彼女は深尾さんの一周忌に、詩と我が家の春の菫をささげ、
それが必ず亡き人に我が心意気として、「嘉し」と受け入れられる事を疑わないのだ。
それは高価な市販の花輪のいずれにもまさってあまりあると疑わないのだ。
彼女の方が筋が通っているなあ、と、私は思った。
なぜなら私が捧げるのは喪主が一回忌を行う事へのあいさつにすぎず、
さればこそ、金額を見比べようとしたではないか。
彼女は深尾さん自身に捧げた。それでよいのだ。私らは詩人であり、だからこそ
「花壇をささげる事はできず、しかし菫の一株がそれに匹敵することがわかっている」筈だからだ。
縛るもの
a 農村で
東京では自分の意思で友人を選びわけ、近所の人でもつき合わない事もできた。
田舎ではその圏に入りきる事によってはじめて生活が成りたつので、夜があけると共に
その秩序はすでに自分を縛って居り、自分を周囲からとり出す事は到底できなかった。
ただ夜の時間だけは自分のものにしたいと、家人たちが寝てから読みたい本を読み
昼間麦を刈りながら思っていた事を作品にし、いつの間にか暁近くまですごした。
夜があけると共に起き出る農村の人々は早い。おくれないよう鍬をかついで畦をゆく時
つい眠気のために目をつぶって居り、しばしば泥田の中へ落っこちた。
しかし夜は夜で全力をあげなければーーーー。
つまりほかの時間にはできない事をするのだから。
何度も泥田に足をふみはずす私は、目にみえぬ束縛に対し、肉体をもってする
無意識の抵抗をしているのにちがいなかった。

幼きものの世界
b 赤いスカート ー ノブコ
つとめから帰ってくる私を迎えに
ノブコはいつもバス停留所へむかいにでていた。
ママが病気のあいだノブコは二ヶ月私とくらしたのだった。
はじめ打ち合わせていなかったので買い物の都合で私は
一つ手前の停留所で下車し、行きちがいになってしまった。
お互いに探して暗くなってからやっと逢えた。
次の日ノブコは私を見落とさないよう、マルゼン石油の
注油所の高い高い階段の上で私を待っていた。
垂直に近い梯子のような階段をうしろ向きにいそいで降りてくる赤いスカート。
あぶないから これからは決してあそこへ昇っちゃいけないと
私はノブコにきつく云ったが、
その赤いスカートは私の心にいとしく強くきざみこまれた。
継ぎ
延々と継当てされたモス地は、同時代の人の手によるもの。
母が無くなったあと箪笥の中に下着はすべて白くたたまれ、
そして沢山のこまかいきれいな継ぎがあたっていた。
戦争の間、衣料はすべて不自由であったから、どこでもそれは同じかも知れぬ。
でもあまりにきれいな継ぎ目故に、母は自分より高い高い人のように思われた。
オリンピック
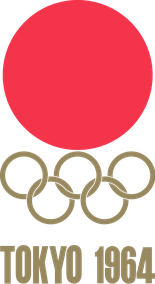
記録の中に勝ちとる孤独
記録の中にかぎりない失墜
段々をのぼっていって点火した時
いぶりはじめた犠牲の心臓
季節はいまや沸騰して
ルールはタイムウオッチにきざまれる。
旗は空の碧瑠璃の中に
赤黃緑の祖国の夢を描きつづけ
さびしいさびしい故国の高原の風が
黒檀色のふくらはぎにまきつく。
勝つのは一人だけ、あとは負けのための
祭りの中の屠殺場、その巨大なコロッセウム
吐きだしの精神のきわまった時
追いつめの舌とともにゴール
勝つための喝采と
負へのあくたいの等価値
選手には顔がない自意識もない
ただ力こぶと腱で吊りあげるメダル
花火は空に瞬間留められ
打ちふるハンケチは汗の匂いの靄をつくるが
時は忽ち過ぎて花と実は同時に地に散らばり
チャスラフスカの青春は今終わった。
なぜこんなに

なぜこんなに心がいそぐのだろう
まるで11月に枯れる一本の草のように。
まるで太陽のやさしさがなかったら死ぬ昆虫の運命のように。
寒い風の中で私は耕す。
まるでリヤ王かマクベス風な荒天の下で。
髪をゆわえた三角巾のはしが
はたはたと耳もとで鳴る。
鳥のように叫びたいとまねて
樹々がはばたきをするようにーーー。
私の心は唖(*)なのだ。
手がこごえはじめる。
涙が流れはじめる。
もう誰一人見えない夕ぐれに
いつの間にかさびしく残されて、
そしてこれが私に丁度よい事と思って。
*原文のまま
焔に薪を
生家の庭にて
天性的に非常に詩人的な人は
自分の才能を信じすぎ
詩を「新らしく」つくる努力をしなくなる。
昔の称賛が耳にあり
今の世の中の詩を見下げて
「自分の今の詩」をみつけなくなる。
死ぬまでのびれば それこそ天才だ。
焔に薪を加えていくように
今まで詩じゃなかったものが だんだん加わらなくては
本当の天才にはなれないのだ。
素描(B)
コップのお茶の中へ
角砂糖を落としてやった時に
それはみるみるとけはじめた
菜穂はあわてて救はうとしたが
匙の上で最後の角が消えてしまった
彼女は驚いてみてゐたが急に匙を投げだして大声で泣きだした
おおなんと我慢のない角砂糖よ
パンやビスケットならもっと堪えるのに
お前はたよりない、情けない
しかし変わった事で泣いた菜穂よ
お前は全くよく泣いた
大人の世界では消えないものもない位だとは お前は嘸かし知らないだろう
しかし大人はそんなことに泣くことさへ忘れてゐるのだ。
お前の涙を私はきっと忘れまいよ。
* 読点は9行目にひとつ。 句点は最後の2行にしか付いていません。
地方人
b松風のごとく
福田英子(ふくだひでこ)の碑を建設しようと、はじめ女性ばかりで相談していたが
もっと広く呼びかけなくてはと、協力して貰えそうな人々に集まってもらった。
その中に明治の自由民権運動の生き残りとして最年長の余公芳太郎さんもいた。
しかしその集まりでは何をおいても早く建てようという側と、彼女に関する著書や講演で
まず一般を啓蒙する方がさきだとする側と二つに別れた。
前者を実践型、後者を知識人型とでも云おうか。
建碑がゆきづまり、頓挫している時、何かの用で新西大寺町を歩いていると
とある古美術商の店から余公のおじさんが飛びだして来た。
「おいおい永瀬さん、うちの前を素通りするちゅう法があるかい。」
「あらおじさんここだったのですか。つい知らずに、、、」と云ううちに彼は
道のまんなかにつっ立って「うちは今日は休業にするからなあ」と
大きな声でそこらじゅうに聞こえるようにどなった。
「一体どうしたのですか」と私が云うと彼は、
「今日は一日国会とか云うて、東京からおレキレキが大勢県庁へ見えるんじゃ」
と云いながら県庁の方向へむいてグイとアゴをしゃくった。
「俺はしがない道具屋で、何も知らん馬鹿から高い銭をふんだくるのが商売じゃ。
ところが そのドロボー稼業では国会のおレキレキにはかなわんのさ。
大親分のご入来じゃからコチトラ尻尾を巻いて休業じゃ」と
なおも大声であたりに聞こえよがしにどなった。
私はクスクス笑いながら年をとっても昔のままの彼のあとについて店へ入ると
彼はまた改まった顔で「英子の碑の件はあれからどうなっているんじゃ」
「それがご存じのように意見がわかれて、、、、、」と私が云いかけると彼はきっとなり
「お前、誰かに頼んで建てようという気とちがうか。
それにお前は知事に取り入っていると噂があるが本当か」
「馬鹿なことを。県庁につとめているのと、取り入るなんてことは全然別ですわ。」
「それならいいが、英子の碑を建てるつもりなら、誰にも云わんとお前一人でやれ。
『思う者』だけでやるんだ。お前と俺の二人でやる気があれば、俺は知った石屋にも話して、
なあに五、六万円もあればできるよ。除幕式に手拭いくばろうと思うな。
折り詰めなければ来んような奴には来てもらうな。おい。それでやるのかやらんのか」
と彼は私につめ寄った。
私は
「それじゃあおじさん、今お金下さい。そして『その気』になる人をもすこし探して下さい。
私はぜひやりますから」と云った。
彼は「よし来た」と云いながら「まずお前、その気の奴を三十人見つける事だ」
と財布から二千円だした、、、、。
勿論その時と云えども、六万円では碑はたちにくかったろう。
けれども私は彼の言葉に錐でももみこむようなものを感じた。
そして結局次の年の四月 笠井山の頂上にその碑をたてる所へ漕ぎつけた。
けれどその除幕式の日には名もなき道具屋の余公のおじさんはもうその一生を終わっていた。
「誰にも云わんとお前一人でやれ。『思う者』だけでやるんだ」という彼の声はしかし
笠井山の松風のように私の耳にいまもきこえてくる。」
みえるものについて
a 澄明な空気
久々に田舎の家に行き、片づけのため表戸の鍵をあけ、窓をあけ、
さて荒れた草庭をながめた時、ここに住んでいた十五年前の心が戻ってきた。
その時、秋の空はまぶしく晴れていたが、私は地味なグレイまじりの青と紺の
木綿のブラウスを着ていたのに、気がつくと今やそれは教会のステンドグラスのように輝いて居り、私は窓辺に、奇蹐に逢った人のように驚きつっ立っていた。
草庭をくぎる石垣にはマサキの実が房のように纏絡し、透きとおる紅玉のような
まぶしい硬質の光を発射していた。思いがけぬ光の氾濫とその鮮度。
都会にいる者と、田舎にいる者は、空気の鮮度がかくもちがうことに
お互いにその中に溺れている故に気がつかない。
だからその差を測定する事はできないし、勿論 私が田舎に以前住んでいた時
その事をはっきり認識する事はできなかった。
たまたま都会から久しぶりに帰って来たので、私は初めてそれらの事に驚いたのだ。
私の着ているものがそのようにも美しいことを、都会ではその曇った空気の故に、
蛍光灯の故に、絶対に気づかぬとしたら、精神の内部にあるものにしても同じ事がある筈だ。
私は畳の古びた昔の家をあけ放ち、
自分の古い詩稿、友から来た古い手紙を抽きだしの中からかき探し、
それらによって、都会において私が受けている鈍化を自分は決して気づかず
そして、昔かぎりなく孤独の中に輝いていたものの光を、
今はじめて自分は受けとりつつあるのだと感じたのだ。
ある持論(ニ)
最初はかすかな予感である。
次第に揺すれリズムが生まれる。
それは詩人の中にあるのだが、肝心なことは
読者の中にも生じると云うことである。
リズムの存在は受けとり方をスムーズにし
又、脳髄へのきざみこみを確かにする。
しかし出来合いの、あり合わせのリズムは、読者をより早く嫌悪させる。
リズムは詩人の産む内容に深く拠って居り
一種の共鳴状態を読者に起こす時のみ、それは成功と云える。
いま現代詩においてはリズムのことは忘れられている。
ありがとうよ、にいさん
印の場所が「アルメニア」
「僕がもう店をしまおうとする時間になって、天使のような顔つきの黒人の若い女が
傷んだ野菜の屑の中をかき探しているのを見つけた。
きっと屑の中でましな野菜をさがし、それで家族の夕食を安くあげようとしているのだ。
僕は近寄り、キャベツの大きな玉を彼女にさし出してやった。
『ありがとうよ、にいさん』と彼女は云った。
『だけど結構。私はただ少しほうれん草をさがしているだけなんだから』と彼女は云った。
勿論その時、僕はキャベツのかわりにちゃんと立派なほうれん草を、
紙袋ごと彼女に与えることもできた。
けれど僕はそうしなかった。なぜならそうすれば彼女の趣旨に反すると思ったからだ。
僕はただ、どうにもならない笑いを笑いながら、彼女をながめ佇んでいただけだった」
(「サローヤン短篇集」)
彼女は拒絶によって、はかないわが人格をかばった。
たとえそれが傷みかけたほうれん草によってであろうともーーー。
私は黒人女の言葉を忘れまいとくり返し読んだ。
「ありがとうよ、にいさん。だけど結構。」
私はその云い方にほれぼれし、
そう云うことが必要な時には誓って私も同じ云い方をしたいと願った。
なぜなら黒人の彼女と、アルメニア人の彼に、
たとえ野菜をあさっても理由なく物を恵まれる事を拒絶し、
心の独立を守る事はどんなにか大切なのだと教えられなければ、私は、
日本人の私は、ついついほだされ、人の顔をつぶすまいとはばかり、つい安きに、
つい得をとり.......するからである。
「○○のご褒美に、お前に何億円やるよ」
「ありがとうよ、おじさん。だけど結構」
ああ私は始終練習して、まさかの時、そのように云いたいのだ。
流れるごとく書けよ
詩をかく日本の女の人は皆よい。
報われること少なくて
病気や貧しさや家庭の不幸や
それぞれを背負って
何の名誉もなく
何年も何年も詩をかいてゐる
美しいことを熱愛しながら
人目に立つ華やかさもなく
きらびやかな歌声もなく
台所の仕事にもせいだして
はげしすぎる野心ももたず
花を植ゑたり子供を叱ったり
そして何年も何年も詩をかいている。
先生もなく弟子もなく
殆ど世に読んでくれる人さへなくて満足し
風の吹くようなものだ
雀の啼くようなものだ
しかし全く竹林にゐるやうなものだ
あゝ腐葉土のない土地に
種をまく日本の女詩人よ
自分自身が腐葉土になるしかない女詩人よ
なれよ立派な腐葉土に。
あらゆることを詩でおもひ
あらゆることを詩でおこなひ
一呼吸ごとに詩せよ。
日記をかくやうにたくさんの詩をかけよ
手紙をかくようにたくさんの詩をかけよ
失へる日に歔欷の詩を
逢遇の日に雀躍の詩を
無為の日に韻無き詩を
培かへる日に希望の詩を
恋人のためにわが髪の詩を
子供のためにほおずりの詩を
兵隊のためにマーチを
時々刻々に書き書けば
成りがたい彫心 鏤骨の一篇よりも
更に山があり谷があり
貴女の姿のまるみのみえる
逆説的の不思議はそこに
普段着のごとく書けよ
流れるごとく書けよ
まるでみどりの房のなす樹々が
秋にたくさんの葉をふらすやうに
とどめなくふってその根を埋めるやうに
たくさんの可能がその下に眠るやうに。
オオバコの花
永瀬の庭に生えたオオバコ。花のあと。
新しい広い農道が出来たので人々は以前の畦道を通らなくなった。
或日、久々にそこを通ったら、道のまんなかに立派なオオバコの一株がおごっていて
今は踏みつけられぬその株は、葉脈もふかくきざまれそして花盛りだった。
オオバコの花なんて今までろくに見た事もなかったのに
沢山のうす紫の花がまぶれついて居り、よく見ると
花はちらちらとゆれていて今にも鳴り出しそうに見えた。
しゃがみこんでじっとみつめていると
オオバコの花茎は、だんだん立派な塔のように見え、ぶら下がっている花々は
まるで風鐸がその四方の軒にさがっているような塩梅だった。
立派な立派な構築物だった。
だまして下さい
1952年12月に出版されたもの
「だまして下さい言葉やさしく」と言う詩は、私の今までの詩の中で
一番人に喜ばれた詩であった。 朗読された事も一番多い。
然し一番最初に ある綜合雜誌の乞いによって これを送った時
「御作は甚だ結構で御座いますが、
当方は何分綜合雜誌で御座いますので、
あまり女心のキビをうがったようなものは適しませんので、
どうかその点お含みの上かわりの御作をいただきたく存じます」と書いて来たのだった。
私は
「この詩は私の全力でかいたものですから これで御気に入らなければ
私自身がお気にいらぬも同じで御座います」と返事した。
そして綜合雜誌綜合雜誌と高級ぶった云い分を嗤(わら)った。
高村光太郎氏が ある時夫人のことを
「智恵子は画家でしたが、僕が彫刻家としての立場から
あまりに厳しくその絵を批評したのを 今から思うと可哀想なことをしたと思います。
芸術家には称賛ということが必要なのです。その事によって心をゆたかにされ
のびてゆけるのです」とおっしゃったことがあり深く心を打たれた。
「だまして下さい言葉やさしく」は結局その事を云いたかったのだ。
たとえ架空の言葉であろうとも、愛の称賛ほど自信と力と叡智を生むものはない
と云う事を云って、私の心の欠乏を訴えた詩であった。
この詩に涙を流したと云って下すった方がニ三あったが
それらは全て中年以上の方であった。
或いは中年をすぎれば、誰の心にもそうした願いがあるのではなかろうか。
賣笑婦(*)の言葉のようにしか解釈できない若い編集記者は気にかけないとしても
私が若さなど大したことに思えないのも そのためだ。
(*)原文のまま
田と詩
蔵の中で眠っていた未開封のインク
カートリッジに変わった頃に予備としてあったものか?
二反の田と五寸のペンが私に残った。
詩を書いて得たお金で 私は脱穀機や荷車を買った。
もうどちらがなくても成り立たないのだ。
私の詩は農繁期に最も多く降ってくるのだ。
しばらく田に出ないでいると何も書けなくなるのだ。
牙のある動物が牙をとぐように
田で働かなくては書けなくなるのだ。
月の輪音頭
岡山県美咲町(旧久米郡棚原町飯岡)の月の輪古墳発掘の成功を記念して作られた
「月の輪音頭」は作詞:永瀬清子 作曲:箕作秋吉 によりもの。
歌詞はH19年に田原清美氏がSPレコードから確認されたものを
転記したものです。
1 月に輪をかく月の輪踊り
(サッサ踊ろよシャシャントシャント)
そろた心が輪に咲いた
ヤンレ今夜の ひと踊り
2 思いだします茨をわけて
(サッサ踊ろよシャシャントシャント)
石に流した あの汗を
ヤンレなつかし ひと踊り
3 鍬をかついで もっこを負うて
(サッサ踊ろよシャシャントシャント)
学ぶ歴史は手とからだ
ヤンレ先生も ひと踊り
4 高い山から谷底見れば
(サッサ踊ろよシャシャントシャント)
月に吉野の瀬が光る
ヤンレ涼風 ひと踊り
5 遠く近くに友呼び交わし
(サッサ踊ろよシャシャントシャント)
ひびけ つくした心いき
ヤンレみんなで ひと踊り
6 二人揃うて眠りは深い
(サッサ踊ろよシャシャントシャント)
夢は千年つかの間に
ヤンレ万年 ひと踊り
7 はにわ運んで 葺石ふいて
(サッサ踊ろよシャシャントシャント)
稗を食うて穴にねて
ヤンレ可愛や ひと踊り
8 夜霧朝霧 湧く里なれど
(サッサ踊ろよシャシャントシャント)
今じゃ天下に名も高い
ヤンレどうじゃ ひと踊り
鷹の羽
母親、清子の手で繕われた長男の制服
子供は山で一枚の大きな鳥の羽を拾って来た。
それは美しい不思議な だんだらがあり
あたかも生気にみちた自然からの
飛沫のようにつやつやと光っている。
これはたしかに鷹類の羽にちがいない。
富士の見える松の木の高いところに棲んでいる。
目玉のギョロッとした あの鳥のものにちがいない。
風と共に空を翔けり
獲物を発見するや忽ち急降下してくる。
あの壮んな鳥のものにちがいない。
お母さんは小さい時に読んだ。
金色の羽を拾ったために数々の冒険に出会う若者の
長い運命的な物語を。
あれは多分スラブの民話だった。
たしかに鷹の羽をみていれば勇敢で冒険的な
矢のように はやる気持ちが湧いてくる。
子供よ。
お前は珍しいものを拾って来て
うんと元気な子になりそうだ。
お母さんの知らない世界を どんどんゆきそうだ。
お母さんに出来なかった事を沢山しそうだ。
頬の紅い子よ
我子よ。
絵葉書
「永瀬清子の世界」より
「靴下の傑作」
- 壺井栄さんの手編 -
昭和十年冬の会合で、はじめて壺井繁治さんの隣に座った事があった。
会場は休んでいる寄席の客席で、男の人たちはみなあぐらで座っている中で
壺井さんの靴下が毛糸のすばらしい手編製品である事に私の目がはたととまった。
それは心打つ靴下であった。
きちんと揃った網目、指やかかとの増目へらし目が、履き良さそうに具合よく
また全体が誠実丁寧に作られ、そのバランスもすばらしいものであった。
誰が一体このように親切な作品を作ったものかと、私は感心しつつ
その場のテーマが文字上のリアリズムとロマンチシズムを中心に
現状を批判しているので、とうとうその事は聞くひまなしに別れてしまった。
するとそのすぐ直後「新潮」をみていると、小説の新人として壺井栄さんの写真がのって居り
それは日のあたる縁側で、素朴な丸顔の栄さんが編み物をしていられる所で
写真に添えられた文章では
「今まで文学をやる事などすこしも考えず編み物ばかりしていた私は夫が検挙された留守中
佐多稲子さんなど友人に『あなたはきっと書ける人だから』とすすめられ
はじめて創作を書いたのです」という意味が書いてあった。
また本文の創作は「大根の葉」だったと思うが、夫が刑務所にいっている間の事が書いてあり
一夜にして桑の葉が霜に散り落ちる情景が印象に残った。
それらによってまさしく先夜の見事な靴下は、栄夫人の作品である事をさとったのであるが
本当の事を云うと、繁治さんの作品には「なるほど」はあるが「好き好き」の魅力まではない。
彼はあの靴下をはたして越えられるのか、と心の底でふと私は思っていた。
.........................................................................................................(略).....................................
栄さんの良さはすべて手作り仕事のよさで、おいしい味噌汁をつくったりお漬物もよいのがあって
私はよばれては感心した。小説もみるみる評判になっていった。
繁治さんは詩の世界ではそれなりに働かれたが、靴下をどれだけ抜かれたか。
もちろんはじめからこれは困難な比べ方にはちがいない。が、一目で靴下に見とれたことは
まず世の中に珍しい事だったのではないか。
* 壺井栄さんは毛糸の編み物で家計を助けていたそうです。
「都わすれ」

さるとりいばら
東京へ帰りたくない?と人がきく
田舎で暮らすことなど到底都会では考えられなかったが
いまの私の藍色の山々で自分をびっしりとりかこみ
小さな自分の田を耕して木埋と方言で暮らしている
東京へいったとて何がある
昔の東京は済んでしまった
会いたいものがなければ行く事はない
ぜひ逢いたいものがあれば会えない方がよい
逢えないためにペンがすすめば田舎の灯の方がよい
ああ東京へいく事はやめよう
心のかぎり逢いたいものは戦火とともに逝ってしまった
たとえ都会へ行ったとて時の瀑布はのぼれない
まわりに人が多ければ沈殿物(おり)がたちまよい
自分を透かしてみる事は出来ない
あぜの草は土の上にぴったり星型に紅葉し
田舎の空気は燈明に結晶して今まっしろにひびが入っている
私の冬の仕事は田んぼの土おこし
それは次の季節のため
自然のめぐりと同じ位必要なのだ
私のあすの仕事は大盛上山の植林
それは何十年さきのため
自然のめぐりと同じ位必要なのだ
古い株や枯れ草を燃(*)きはらい
その焔がおさまって山がすっかり冷えた時
そのあとへみずみずしい苗を植えるのだ
山々にかこまれて私はもう都会の誰からも見えなくなり
都会の磁気はいまや私を圏外にして空しくはばたいている
船出した都会へは再び帰らなくていいのだ
私の孤独や悩みはあり得ないものに属し
さるとりいばらや枯れ羊歯の線条と等しく
早春の山のうす煙となって自意識は透明な風の中を渦巻き去るのだ
(*)「燃」は原文のまま
「我を忘れて」
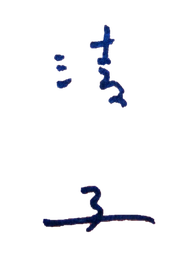
我を忘れて暮らすこと
それができるかできないか。
悲しみに声かすれる事も
好きな本をただ一晩で読む事も
橋のない所をまっすぐに歩いていって
向こう岸へまっすぐ着けるかどうか。
それさえ考えず、読みさしの本が濡れずに着けるかどうか
それがすべてだ。
年とったとか、日が暮れたとか、
そんなこと忘れてくらせるかどうか
それがすべてだ。
「一升枡で」
一升枡で米や麦を量るのに、一升あればよいのではない。
うんと山盛りにしておいて水平にスキッとはらう。
それは詩の方法でもある。
事実に正しくとだけ願っていては米は量れない。
山盛りをみて人はオーバーだとか虚妄だとかそしる。
その盛リ過ぎなしに詩がまちがいなく本心をとどける事は困難である。
「唇の釘」
唇のわきには小さな釘がしかけてあるので
文楽の女形人形はそこへ袖口をひっかけて
いつもよよとばかりに泣きしづむ
雨にぬれた葉草のようにみよもあらずぺちゃぺちゃに
本当の人間であればそうした釘はないから
自分の歯で
泣くまいとこらえて力一杯噛みしめる
戦地から帰る善の夫のため新しい布団を
四十数年 新しいままにしまっておいたおばあさんもいた。
布団ばかりじゃなく袖も手拭きも
泣き声出さぬためのかんぬきになるのです。
自分の心を出し切れず
無理無体に大事な者をとられて
泣くな女よ
泣くな泣くな女よ
乳児の時の歯がほろりと欠け落ちるように
私らの唇のわきの釘は
もうなくなるのがいいのだ
世の中にはたくさんの言葉が山とあるのに
どれ一つ自分の心につながないということがあろうか
コンセントを探せ そして理不尽な世の中へはっきり云え
私らは愛する者と生きたいのですと
自由が来たように
釘はいらぬようにみせかけて
やはり聞こえてくるおどし文句
まだ涙はふききれぬのに
遠い親と子は探しあっているのに、、、
物云うための唇だ
唇は寒くあってはならない
噛みしめるためにありはしない
お主のために泣いたり
家や世間のためにしばられたり
いつもいつも唇のわきの釘が必要だった
花かんざしをふるわしたり
白い襟足をみせて泣いた
泣くに慣れるな日本の女
今はもうそれがすんだと云うならば
本当のよろこびは来たのか
理不尽はもう絶対にしないとでも云うのか?
私らの望みはもうすぐ実現するとでも云うのか?






















